本宮版三国志『天地を喰らう』とは
高校時代は『三国志』にどっぷりとハマっていた時期でして、吉川英治の『三国志』はもちろんのこと、親からもらった昼飯代をやりくりしては、横山光輝の『三国志』のコミックスを買いあさっていました。
その三国志愛は本宮ひろ志版の三国志である『天地を喰らう』をも当然網羅しており、ジャンプ連載時(1983年~84年)には小学生だったために

ちょっと…よく意味がわからない内容だな…
と感じていたこの作品も、数年後にあらためて愛蔵版のコミックスを購入することで

なんだこれ、めちゃくちゃおもしれーじゃん!
なんで連載打ち切っちゃったんだよ!
と、その作品の面白さを再確認していたのです。
…こんなマンガだったんですよ。かなり荒唐無稽で天界とか魔界とかまで出てきちゃうんですけど、そのスケールの大きさがまた本宮先生っぽくていいんです。
魔界編が終わった後は一応通常の歴史モードに戻るのですが、呂布、董卓と、登場するキャラがいちいち強烈に描写されているので、ひじょうに印象深い作品となっておりました。
勝負師! カプコン!
ですので、このタイトルがアーケードゲームとしてリリースされたときはびっくりしましたね。
それはどちらかというと

まさか『天地を喰らう』がゲームになるとは…!
という、意外性のびっくりの方でした。
というのも、『天地を喰らう』は数年も前に連載が終了した上に、爆発的に人気が出た作品ではなかったからです。
そんなどちらかというと“知る人ぞ知る”というマンガの版権をわざわざ取って、敢えてアーケードゲーム化したカプコンの勝負師ぶりにびっくりしたわけです。
しかも当時はこの作品のアニメ化や映画化の話もまったくなかったし、リメイク作品が連載されるという話も皆無でした。つまり、カプコンには何一つ旨味がない版権物だったのです。
ですので、なぜカプコンがこの作品に白羽の矢を立てたのか、いまだに謎なんですよ(苦笑)。
もちろん光栄等の影響で三国志が市民権を得てきている時期ではありました。ですのでカプコンが三国志の世界観をコンテンツとして狙うのは

あるかもな~
とは思うんです。
でもそこで『天地を喰らう』で勝負を賭けようとした英断がすごいんですよ。これ誰がGOサインだしたんだろう(笑)? 相当な本宮ファンがカプコンにいたのかな?
だって企画書を書いて

本宮ひろ志の『天地を喰らう』で行きましょう!
と熱弁しても、絶対に社内の空気は

…そのマンガ知らないんだけど。
本当にインカム稼ぐほどの集客力があるの?
となったはずなんです(苦笑)。ああ、本宮先生、ゴメンなさい(苦笑)。
ですので、この企画がまかり通ったこと自体、奇跡だったのではないかと(笑)。ただ個人的には

カプコン、渋いとこ突いてくるな!
わかってんじゃん!!
と絶賛でしたけどね。とはいえ、これはかなりのレアケースな反応だったのではないか、と思います(笑)。
ファイナルファイトの先輩?
ゲームの内容は、『ファイナルファイト』の三国志バージョンです。あ、元も子もないか(苦笑)。
ただリリース時期としては『天地を喰らう』の方が半年ほど先でしたので、正確には『ファイナルファイト』の基盤を作った“ベルトスクロールアクション三国志”という言い方が正解なわけです。
ですので、『ファイナルファイト』はこの作品のノウハウを生かして、ベルトスクロールアクションの金字塔となった、と言えるのかもしれません。
このタイトルは若かりし日の劉備の義勇軍による黄巾賊討伐から、当時朝廷で横暴の限りをつくしていた董卓討伐までを、その舞台背景としています。
ですのでプレイキャラは
- 劉備玄徳
- 関羽雲長
- 張飛翼徳
- 趙雲子龍
という、劉備自身と早くから劉備に使えていた武将の4名で構成されています。

そして『ファイナルファイト』同様、それぞれの身体能力において特徴と差があり、選んだキャラによってゲームの難易度が変わってきます。
逆に『ファイナルファイト』と違うところはキャラのレベルアップがあり、その成長の仕方でキャラの差別化を行っていました。
レベルアップすると使用する武器がグレードアップするのですが、そのあたりは流行のRPG的な要素を加えている感じがしましたね。
本宮趙雲にホレる
使用キャラはもう、趙雲子龍一択です(笑)。
まず誰がどう見てもビジュアルがカッコいいです。本宮マンガにおける王道のイケメンであり、青い鎧はデザイン的にもヒーローが装着するそれです。

これだけ揃っていると、中二病真っ盛りな年頃としては、彼を選ぶ以外の選択肢はないんですよ(笑)。しかも彼は初心者向けの、扱いやすいキャラでもありました。
また、個人的には

あの本宮趙雲が、こんなに生き生きと動いている…!
という感慨もありました。
というのも彼、マンガの中では登場したとたんに連載が終了するという、とても消化不良な扱いを受けたキャラだったんですよ。
初登場シーンでは2ページ見開きでならず者を正義の剣で成敗するという、めちゃくちゃカッコいいデビューを果たしているんです。
あのビジュアルでこんな派手なデビューをしたものだから、当然私はその時点で

なんか、カッコいいやつ来たーーーっ!!
と、彼の虜ですよ(笑)。なのにその数週間後には連載が打ち切り。
幼心にも

あれ…?
あのカッコいいキャラ(小学生だから名前を覚えられない)、これでお役御免?
と、彼の不遇さに同情したものです。
そんな気持ちを心の奥底に引きずっていたものだから、数年経って彼がゲームとはいえ、主力キャラで画面狭しと大暴れしているのを見たときは、けっこう感慨無量だったんですよ。
そんな幼き日の想いもあったので

あの本宮趙雲が、こんなに生き生きと動いている…!
と感動してしまったんですね。
そしてそんな魅力的な趙雲子龍は、その後の趙雲像に大きく影響を与えたと、個人的には感じております。
特に光栄の『三國無双』における趙雲子龍は、

本宮趙雲の影響を色濃く受けてデザインされたんじゃないかな…?
なんて勘ぐっていますけどね(笑)。
プレイの思い出
ああ、脱線ばかりで全然ゲーム本編の感想を書いていませんでした(苦笑)。
ただ…ぶっちゃけこのタイトルについては、これ以上の思い出はないんですよ。なぜならばプレイが下手くそすぎて、全然先に進めなかったからです(苦笑)。
特に右攻撃と左攻撃で別々にボタンを使い分けなければならない仕様が、私のテクではどうしてもついていけなくて。
ただ面のボスを倒すと、迫力の本宮一枚絵が挿入されたり、攻撃時に

ぬぬぬ! でやぁ!
といったボイスがでるのは印象深かったです。でも…それ以上は…(泣)。

万事がこんな感じだったので、そこを解消した『ファイナルファイト』は、やはり遊びやすいと感じてしまいますね。
その後の『天地を喰らう』
その後、このタイトルは『天地を喰らうⅡ 赤壁の戦い』という続編がリリースされました。1がそれなりに評判がよかったからなのでしょうか。
『天地を喰らうⅡ 赤壁の戦い』では、使用キャラが関羽、張飛、趙雲、黄忠、魏延の準五虎大将となっており、馬超ファンが憤慨した形となっています(苦笑)。
まあ赤壁の戦い時はまだ馬超、劉備軍に参入していなかったですからね。仕方ないでしょう。
さらにはファミコンでもRPGとしてこの『天地を喰らう』がリリースされます。これはかなり遊びましたね。とてもよくできたRPGでした。
こちらもアーケード版同様Ⅱも発売され、どちらも遊びやすくて相当にハマった記憶があります。
このように、初リリース時には

まさか『天地を喰らう』がゲームになるとは…!
という驚きしかなかったこのマンガのゲーム化ですが、結果から見ればカプコンはきちんと版権料分の稼ぎを得たのではないかと思われます。
そう考えると、この作品のゲーム化を推し進めた方の慧眼が、あらためて評価されるべきだと思いますね。
そして本宮先生にしてみれば

まさか連載後に数多くの三国志キャラのデザインをすることになるとはなあ~
と、作品連載中では果たすことのできなかった仕事を、ゲームにおいて成し遂げるという、なかなかイレギュラーなご経験をされたのではないのかな、なんて思いますね(笑)。

















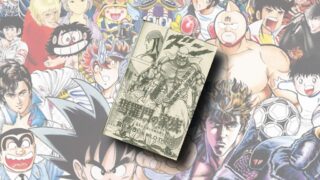




コメント